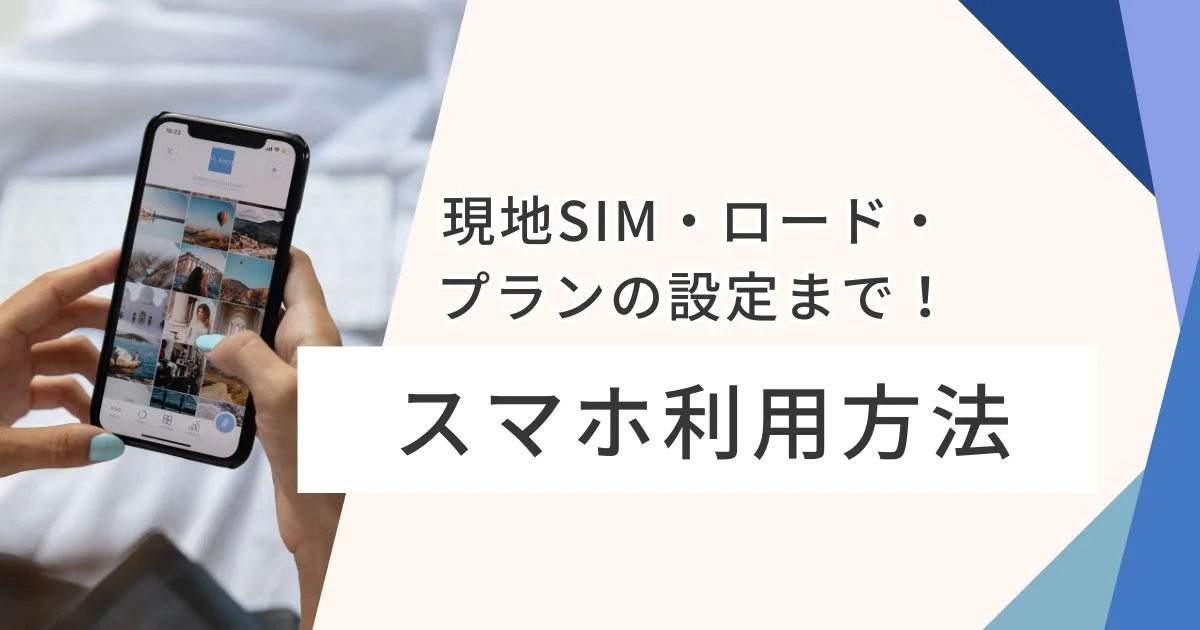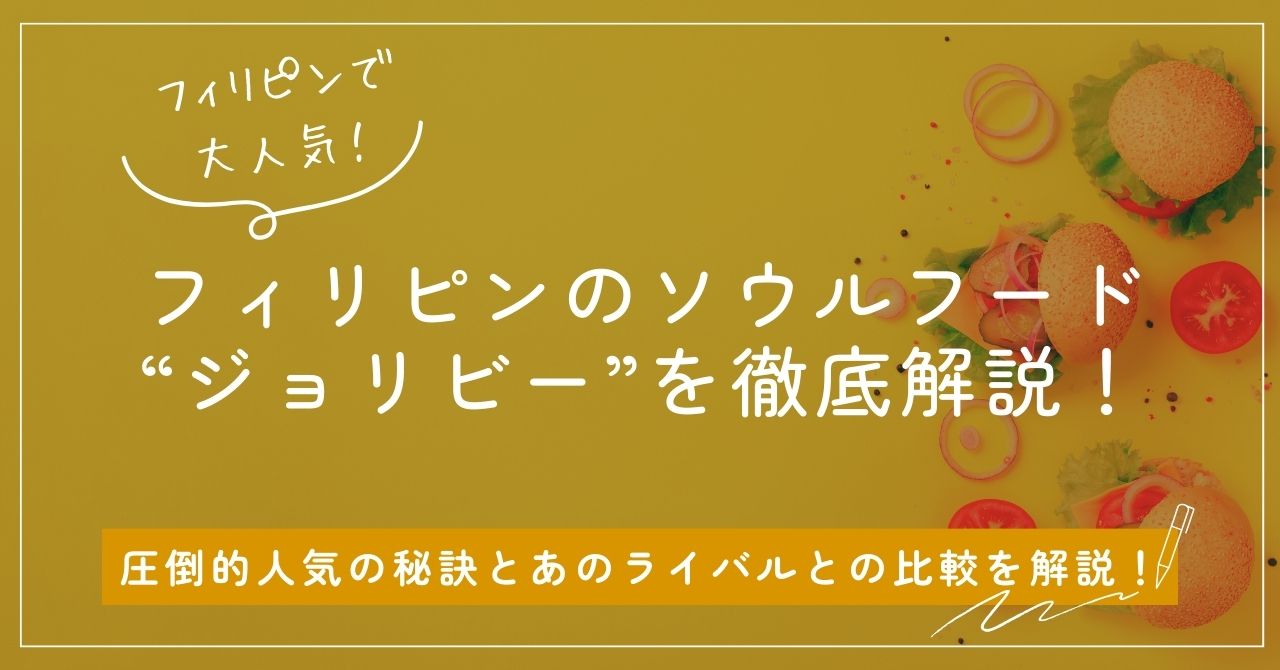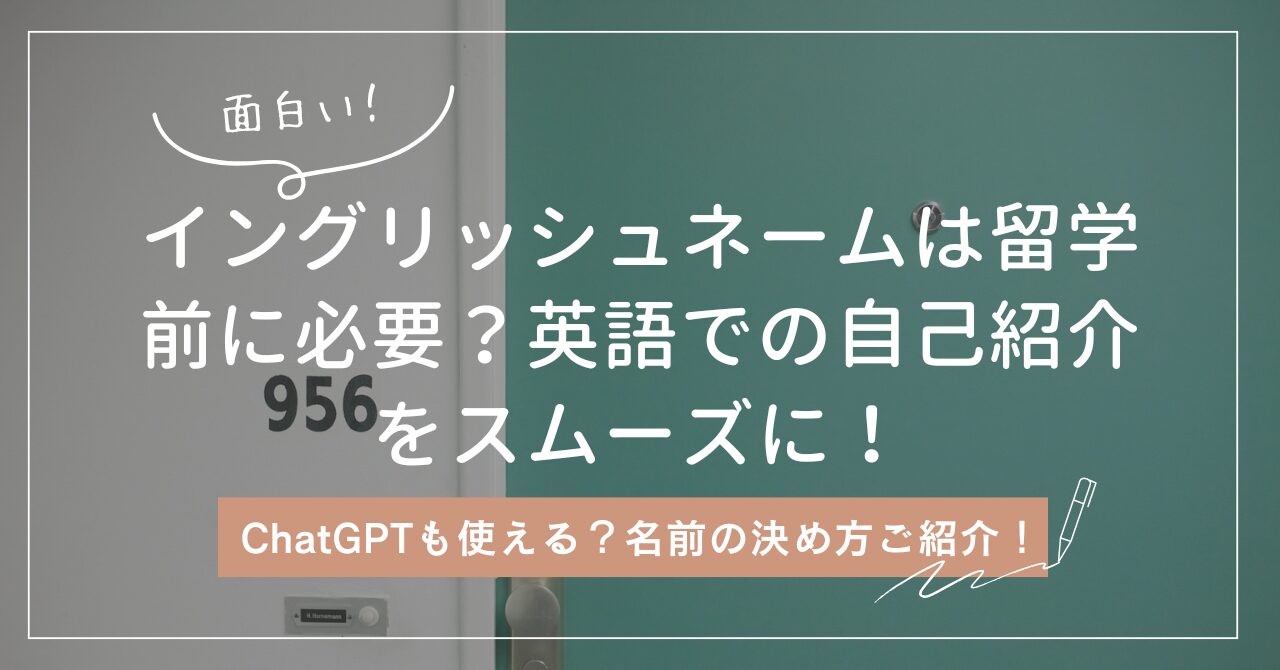子どもの柔軟性を育む、フィリピン留学の魅力

学校では問題を起こすわけでもなく、家でも比較的おとなしく過ごしている。
一見すると、なんの心配もいらないように見える我が子。
でも、そんなお子さんの様子に、ふと気になる瞬間ってありませんか?
言われたことはきちんとこなすのに、指示がないと動けなかったり、予定が少し変わるだけで戸惑ったり。
思いがけない出来事に直面すると、ただ立ち止まってしまう。
実はこうした変化に弱い子供が、今の時代に少しずつ増えてきています。
この背景にあるのは、「失敗しないこと」が前提になりすぎている、日本の教育環境。
正解が求められて、それを正しくこなすことに慣れてしまった子供たちは、自分で考えて動く。という経験を積む機会が不足しているのかもしれません。
「いい子」が変化に弱くなっていく構造
日本の教育では「間違えない」「ルール通りにこなす」ことが評価されやすいという構造があります。
通知表には「指示に従える」「協調性がある」など、型通りに動けるかどうかがチェックされる。
それが悪いわけではありませんが、ただ、その評価軸が偏ってしまうと、子どもたちは「自分で判断して動く」経験を積む機会を失いやすくなります。
最近では、大人が先回りして予定や行動を組み立て、「失敗のない毎日」を整えてしまいがちです。
結果、子どもは“自由に動いていい場面”に出ると、かえって戸惑うようになる。
皮肉にも、きちんと評価される「いい子」ほど、この傾向は強くなります。
指示に従う力はあるのに、予測不能な状況になると動けない。そんな構造が、今の環境の中で静かに育っているのです。
社会はすでに「正解のない時代」に突入している
かつては、これが正解とされる道がありました。
いい学校に進学して、いい会社に就職すれば、将来は安定する。
そう信じられていた時代が確かに存在していました。
ですが、今はというのは、テクノロジーの進化によって、仕事のあり方そのものが変わり続けています。
AIの発展によって、今ある職業の多くが将来なくなるかもしれないと言われ、正社員・終身雇用といった安心モデルも、もはや過去のものになりつつあります。
さらに、国際情勢の不安定さや価値観の多様化により、こうしておけば間違いないという共通の指針すら見えづらくなっています。
大人でさえ、何を正解とするか悩みながら生きているこの時代。そんな中で子供たちに求められるのは、「与えられた問いに答える力」ではなく、「自分で問いを立てる力」ではないのかと考えています。
決められた正解に辿り着く能力ではなく、未知の課題に出会った時に、まず動いてみる力。
うまくいかなくても、修正しながら進んでいく柔らかさ。
それがこれからの社会を生きる上での”地力”になっていくのです。
ただ、その力は一朝一夕では育ちません。
そして、整いすぎた環境や、正解のある世界だけでは、育ちにくい力でもあるのです。
フィリピン留学という「小さな揺らぎ」の体験
想定外が当たり前の毎日
フィリピンでの語学留学には、日本ではなかなか経験できない「想定外」が日常に含まれています。
たとえば、先生が急に交代したり、食事が思ったような味じゃなかったり。
突然の停電でWi-Fiが使えなくなったり。
最初は戸惑う子どもたちも、少しずつ「こういうこともあるか」と受け入れていきます。
それは、不確実なものに対する“耐性”が育ち始めている証でもあります。
すべてが整った環境では得られない、ゆらぎのある日常であるからこそ、「予想通りにいかないことに慣れる」経験が、自然と積み重なっていくのです。
自分で考えて動く、柔軟性のトレーニング
言葉が通じない場面もまた、日常の一部です。
最初はうまく伝えられなくても、子どもたちは少しずつ自分で工夫するようになります。
ジェスチャーを使ってみたり、別の表現に言い換えたり、時には思い切って人に助けを求めたり。
こうした「その場でなんとかする力」は、与えられた正解を選ぶ力とはまったく異なります。
自分で状況を捉え、自分のやり方で解決しようとする即興的な力。それが、柔軟性です。
そしてこの柔軟性は、英語の上達以上に、今の時代を生き抜く力になっていきます。
「正しさ」の枠を超えて、自分のやり方を見つける
小さく枠からはみ出す体験
「いい子でいようとすること」は決して悪いことではありません。
でも、評価される枠の中に収まりすぎると、その枠の外で動けなくなってしまう。
フィリピン留学は、その枠を大きく壊すのではなく、少しだけ「外に出てみる」ための安全な場になります。
いきなりすべてを自分で判断する必要はありません。
小さな即興、小さな試行錯誤のなかで、「自分で考えて動いてもいいんだ」という感覚を取り戻していく機会となる。
それが、子ども自身の行動力の起点になっていきます。
「なんとかできる」という手応えを得る
柔軟性や対応力は、知識だけでは育ちません。
実際に「予定通りにいかない」環境に身を置き、「どうにかする」経験を積むことでしか身につかないのです。
日々の中で、子どもたちは試し、間違え、修正しながら自分なりの方法を見つけていきます。
その過程で得られるのは、「完璧じゃなくても、なんとかなる」という手応え。
それは自信となり、変化の多い時代に立ち向かう力となっていきます。
英語を学ぶ以上に、自分でなんとかできる感覚、こそが、フィリピン留学の最大の成果かもしれません。
まとめ
これからの社会を生きていく子どもたちにとって、「変化を楽しめる力」「正解がない中でも動ける力」は欠かせない素質です。
それは、枠の中にずっといたままでは育ちません。
少しだけ外に出て、自分のやり方を模索してみることが、しなやかさを育てる第一歩になります。
フィリピン留学は、その小さな一歩を踏み出すための、とてもリアルで実践的な環境です。
だからこそ、「うちの子は大丈夫だと思っていた」親御さんにこそ、届いてほしい選択肢だと私たちは考えています。